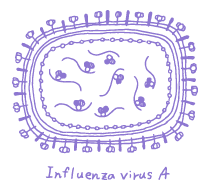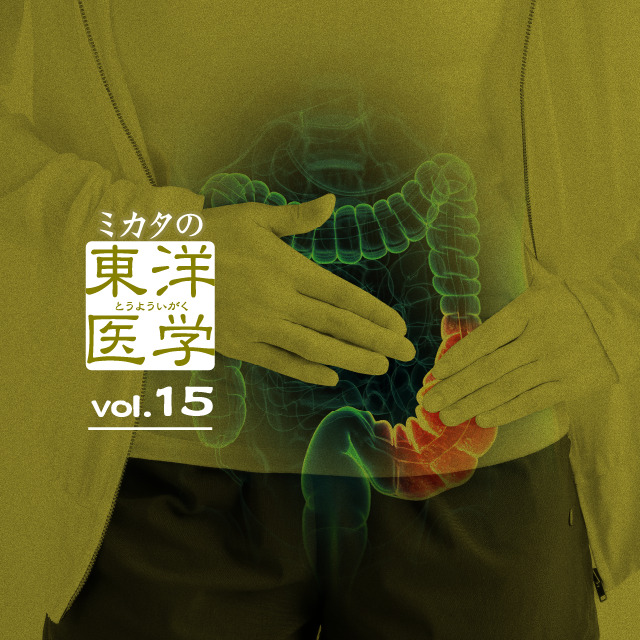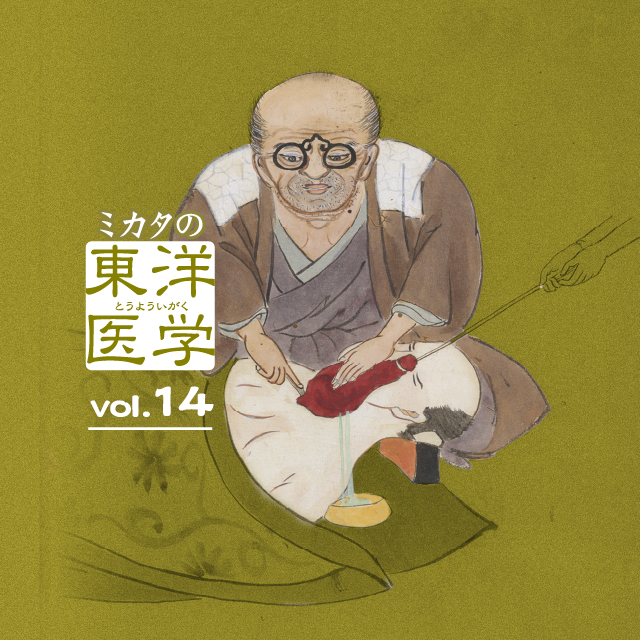夜中までスマホを見続けて目がショボショボ、朝起きても頭がスッキリしない…そんな経験、ありませんか? SNSの見すぎは体に良くないってわかってるけど、なかなかやめられないのが現実ですよね。
そんな現代の悩みを、2000年以上前の中国の陰陽論から考えてみましょう。実は、意外なヒントが隠されているんです。
◆「陽」が強すぎる現代人
2017年にノーベル賞を受賞した体内時計の研究で、私たちの体は24時間リズムで動いていることが科学的に証明されました。夜に分泌される睡眠ホルモン「メラトニン」が重要なのですが、スマホの青い光がこれを強力に抑制してしまいます。
ハーバード大学の研究では、寝る前にiPadを使った人は、紙の本を読んだ人と比べて体内時計が1時間以上もズレました¹。まさに「時差ボケ状態」です。
ここで注目したいのが、東洋医学の「陰陽論」です。
デジタル機器 = 「陽」の塊:明るくて、刺激的で、私たちを興奮状態にする
自然な眠り = 「陰」の世界:暗くて、静かで、体を回復させる時間
古代中国には「日出而作、日入而息」(太陽が昇ったら働き、沈んだら休む)という超シンプルな生活原則がありました²。当時は電気もスマホもなかったので、そうならざるを得なかった。でも、文明の発達で私たちが失ったこの自然なリズムに、現代科学が改めて注目しています。
現代人は夜中までスマホで「陽」を浴び続けて、陰陽バランスが完全に崩れている。これが東洋医学でいう「陰陽失調」の状態です。
◆目と心の深いつながり
韓国の研究で、スマホ依存の人の脳を調べたところ、前頭前野の活動が低下していることがわかりました³。「スマホを見すぎて集中できない」というのは、気のせいじゃなくて脳の変化だったんです。
これまでのコラムでも説明してきた東洋医学の「肝開窮於目(肝の状態は目に現れる)⁴」。目の疲れが全身に影響するという考え方で、現代の眼精疲労から肩こり、頭痛、イライラへとつながる流れと、2000年前の理論がピッタリ一致しています。
さらに「心主神明」の概念も重要です。東洋医学の「心」は血液循環だけでなく、意識や精神活動もコントロールします。スマホ使用による前頭前野への影響は、まさに「心の乱れ」として理解できます。
東洋医学では、体のすべてがつながっているという「全体観」を大切にします。目の疲れ(肝の不調)が心の興奮状態を招き、それが食欲や睡眠、感情のバランスにまで影響する連鎖反応があると考えます。
◆現代版「養生法」で陰陽バランスを整える
じゃあ、どうすればいいの?昔の知恵と現代科学を組み合わせた方法を試してみましょう。
まず「サンセット・ルール」。
日没後はスマホを控えるというシンプルなものです。古代の「日入而息」を現代風にアレンジした感じで、太陽と一緒にデジタルからも離れてみるというもの。
次に「1:1ルール」。デジタル(陽)とアナログ(陰)の時間を同じだけ作る方法です。1時間スマホを見たら、1時間は読書や散歩とか、スクリーンを使わないことをする。偏った陽の気を中和する感じですね。
最後に「自然リズムの復活」。朝は太陽光を浴びて体内時計をリセットして、夜は暖色系の弱い照明で過ごすというもの。自然の明暗サイクルに合わせることで、乱れた陰陽バランスを整えることができます。
いかがでしょう?3つのうちやりやすそうなものから、ぜひ始めてみてください。
◆古代の知恵、現代の科学
最新のデジタルヘルス研究と古代東洋医学が、似たような結論に達しています。人間の健康は自然のリズムに従い、バランスを保つことで維持される、ということです。
スマホは便利な道具ですが、使い方次第では心身に影響を与える可能性があります。これまでのコラムで紹介してきた東洋医学の「見方」を「味方」につけて、デジタル時代を健康的に生き抜いていきましょう。
昔の人たちが大切にしていた自然なリズム。現代の私たちが失いかけているものを、意識的に取り戻してみる。それが、スマホと上手につき合う秘訣かもしれません。
◆参考文献
- Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(4):1232-7.
- 击壤歌 [Ancient Chinese folk song]. circa 2000 BCE; 庄子·让王 [Zhuangzi]. circa 3rd century BCE.
- Kim SE, Kim JW, Jee YS. Smartphone addiction and functional connectivity alterations in the brain: A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2020;118:459-70.
- 黄帝内経霊枢·五官関五味篇 [Huangdi Neijing Lingshu]. circa 100 BCE.
◆「ミカタの東洋医学」バックナンバーはこちらから↓
投稿者プロフィール

- 生まれも育ちも石川県。地域医療に情熱を燃やす若き総合診療医。中国医学にも詳しく、趣味は神社巡りとマルチな好奇心が原動力。東西を結ぶ“エディットドクター”になるべく、編集工学者、松岡正剛氏に師事(髭はまだ早いぞと松岡さんに諭されている)。
最新の投稿
- 2025.07.14ミカタの東洋医学老いにはテンキをミカタに!
- 2025.06.30ミカタの東洋医学デジタル・デトックスは東洋医学だった? スマホ疲れを「陰陽」で読み解く
- 2025.05.15ミカタの東洋医学食事に含まれる謎の物質、約14万種!「医食同源」が証明される?
- 2025.04.03ミカタの東洋医学教えて、華岡センセイ!「便秘の治し方」