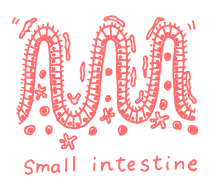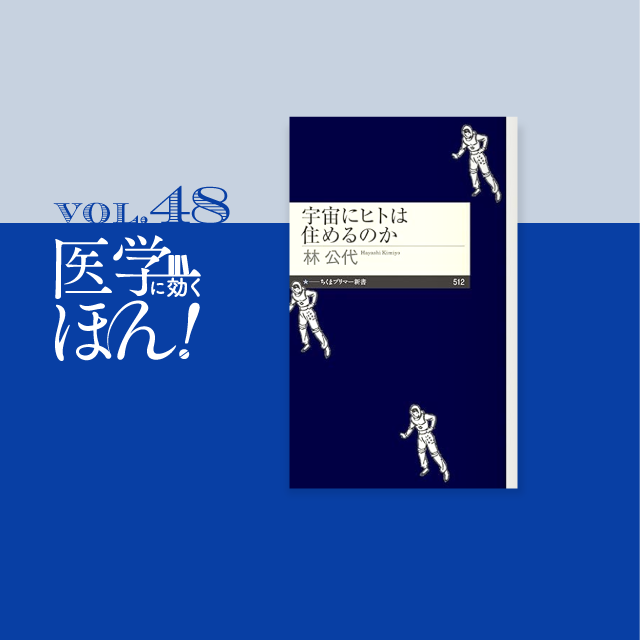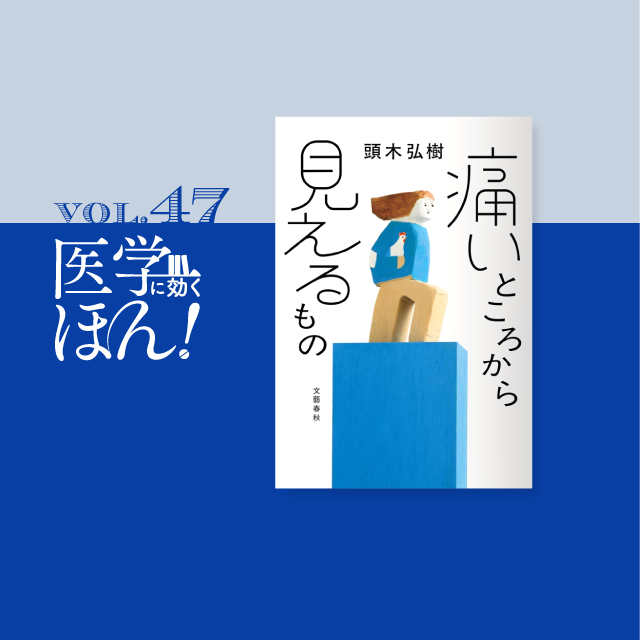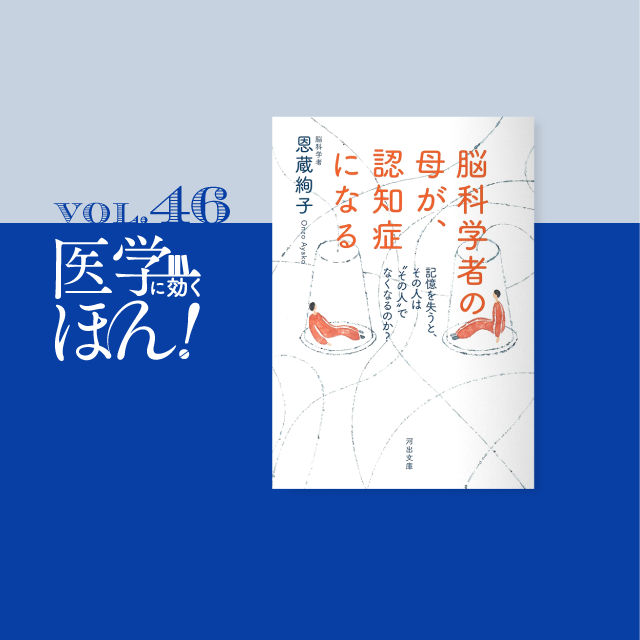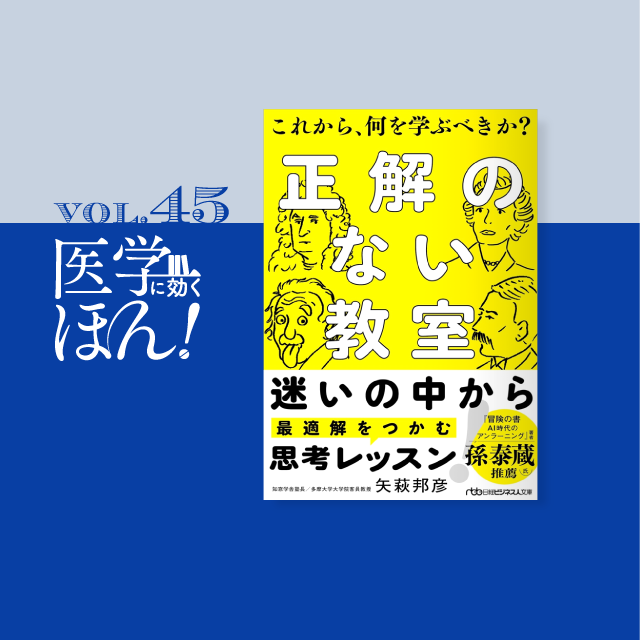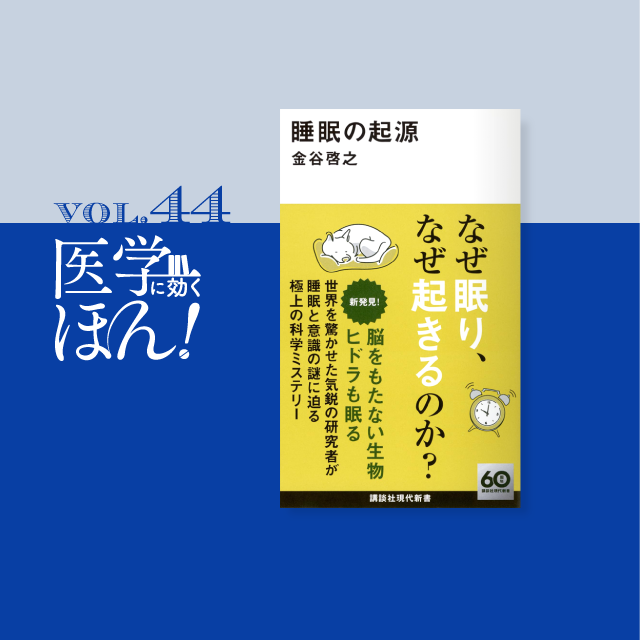「わかりやすさに向かうな! 君の話がいっちばん、つまらん!!」
MEdit Labの活動についての説明の中で「わかりやすく編集工学と医学の魅力を発信したい」と言った私に、生前、松岡正剛さんが、こう一喝しました。
わかりやすい授業。わかりやすいプレゼンテーション。
世の中は、わかりやすさに価値を置くものだと思っていた私は、最初、そうやって叱られたことが理解できず、自分の熱意を否定されたようで悲しい気持ちになりました。しかし、その後、MEdit Labで様々な活動を継続していく中で、「わかりやすさに向かうな」という意味を噛みしめることが多くなりました。
今井むつみさんは、『言語の本質』で一躍有名となった、世界的な認知科学者で、慶応義塾大学の名誉教授。本書『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』は、慶応SFCでの今井先生の講義をまとめた認知心理学の入門書で、その冒頭にはこんなことが書かれています。
本当に大事なことは、例外なく複雑で、難しくて、正解がない。
この言葉にハッとしました。松岡さんに言われたことと同じだなと感じたのです。本当に大事なことは、シンプルにわかりやすくなんて伝えられない。MEdit Labは安易に医学の魅力をわかりやすく伝えるような活動とは距離を置いて、ひとりひとり違って、正解がないような学びの場を構築するべきだ…。改めてそう思ったのです。
◆正解のない複雑な世界
Medicine is an art based on science.
医学は、科学を根拠にしたアート。ウィリアム・オスラー先生の言葉です。アートは例外なく複雑で、難しくて、正解がありません。
病理診断を担う病理医の私たちは、もちろん“正確な病理診断”を目指して、日々研鑽を積みますが、実際のところ、本当に正確な診断なんてこの世の中にはないということをどこかで深く理解していないと、一流の病理医にはなれません。
個々のがん細胞はそれぞれに“顔つき”もふるまいも異なり、それをあらかじめ用意されている診断名に落とし込むことはどこかで無理があるわけです。病気の多様性に対して、言葉はあまりにも足りません。
診断の限界を知り、謙虚であること。その中で患者さんが幸せになる方向に向けて努力を続けることが医師としてのあるべき姿勢です。
医療以外のどんな分野でもそうかもしれません。
本書は、世界をよりよく生きていくための手掛かりとなる認知心理学のアプローチを私たちに提供してくれるもの。人生をより良く生きるための何らかの助けになってほしいという今井先生の想いが込められた講義がまとめられています。
◆アブダクションは、人間の武器
認知心理学とは、「そもそも人は、世界をどう見て(視て)、認識しているのか」の“そもそも”を問う学問であると、今井先生はいいます。
AIと人間の思考の大きな違いとして、今井先生は「アブダクション」を挙げます。フクザツで情報過多の世界で、私たち人間が普通に日常生活を送れるのはアブダクションのおかげであると断言する今井先生。
アブダクションとは、実は、MEdit Labが活動の拠り所としている松岡正剛の編集工学においても重要視している思考方法で、「正解がひとつに決まらない、論理の飛躍を伴う非論理推論」のことです。
アブダクションは、ある種、かなり雑な推論といえます。お母さんに花束を渡したら喜んでくれたから、お母さんはきっと花だったらなんでも好きだ、というような仮説を立てるような感じ。もしかしたらチューリップだったから喜んでいるのかもしれず、ダリアだったら喜ばないのかもしれませんが、日常生活はそういったある種の思い込みに近い仮説を立てることでスムーズに進んでいるともいえます。
でも、一見、雑な推論であるアブダクションは、コミュニケーションを円滑にさせ、学びの質を高め、かつ人間の創造性の源でもあるのです。論理の飛躍を伴う仮説によって、正しい・正しくないを越えた意味の世界、いわゆる“ひらめき”をもたらします。
科学者にかぎらず、医師であっても他の専門家であっても、精度の高いアブダクション推論ができることが一流の熟達者の条件であると今井先生はいいます。
病理診断においても、限られた時間の中で病変の特徴を見極め、あれに似ているな、これに似ているなと推論し、いくつか候補となる疾患名を瞬時にあげていく。その推論の精度を高めるべく、病理医の私たちは日々努力しているといえます。
そのためには、自分自身のアブダクションで得た推論を後で振り返って吟味し、自分の思考のクセを理解するとともに、その推論が論理的にも正しいか検証をすることが超一流になるためには必要不可欠なのです。
◆MEdit Labのワークショップはわかりにくい
今、進んでいるMEdit Labワークショップ「医学をみんなでゲームする」では、毎回、アブダクションを促すQが用意され、ゲーム作りを進めていくプログラムが用意されています。さらに、そのQには、必ずどういうプロセスで回答したか「振り返り」の設問も用意しています。
12段階に分けられたQのひとつひとつは、一見、これってゲームづくりにどんなふうに関わるのかな?とわかりにくいものも少なくなく、あえて、そこは最初からわかりやすい説明は省いて、とにかく取り組んでもらうよう促しています。
まだまだカリキュラムは発展途上にありますが、医学ゲームづくりに限らず、問いを自ら生み出す力、AIに負けない発想力を鍛える力を育む、 “学び方を学ぶカリキュラム”に成長しつつあると自負しています。
正解のないQが用意されたわかりにくいカリキュラム。松岡さん、このカリキュラムの出来はどうでしょう?
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』
- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』
- 2026.01.22お知らせ医療連携ゲーム「ENT!」の行く末は?今年度最後のMEdit授業@吉祥女子中学・高等学校