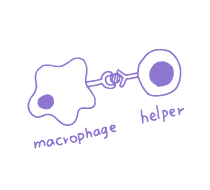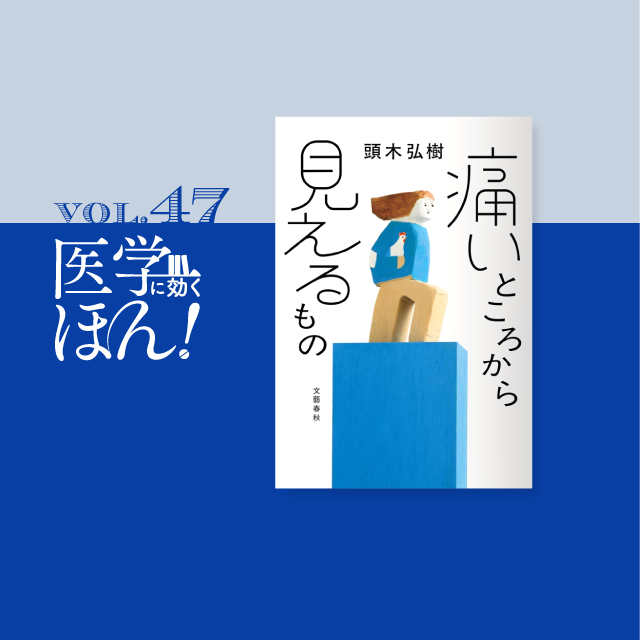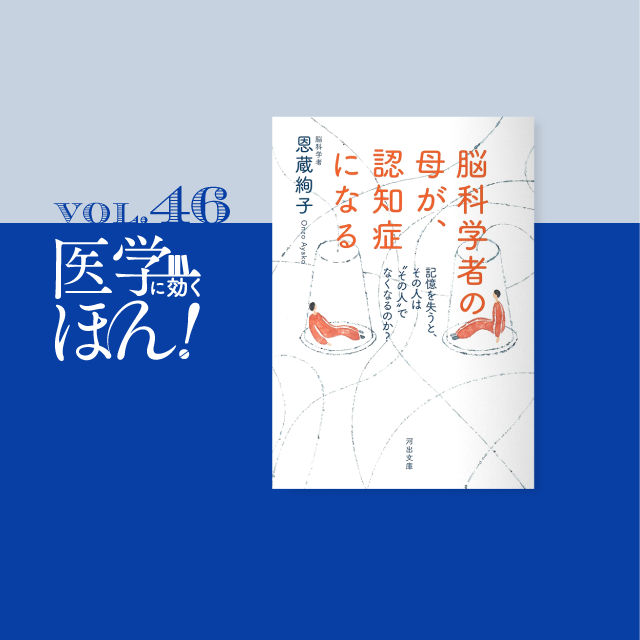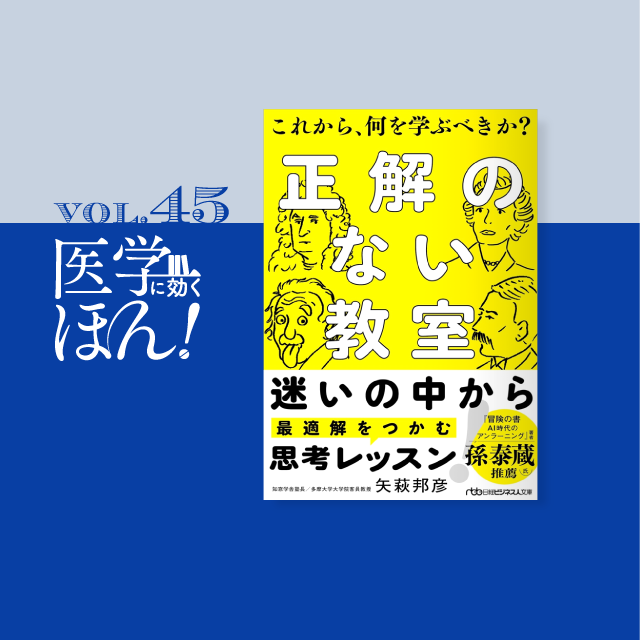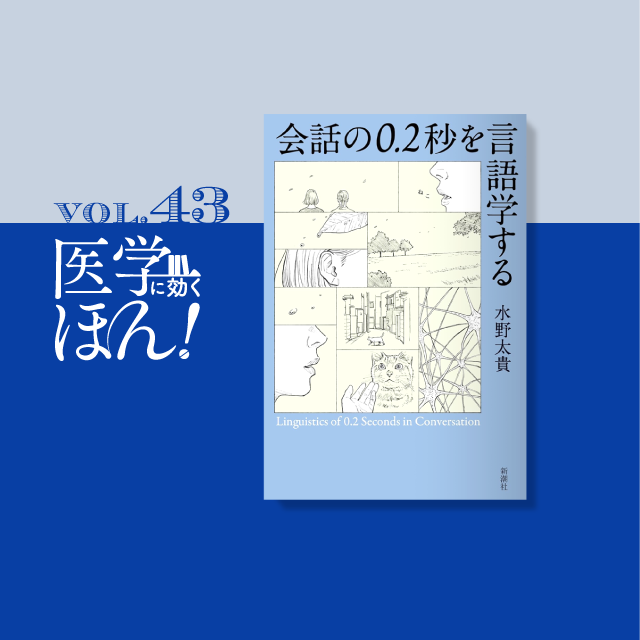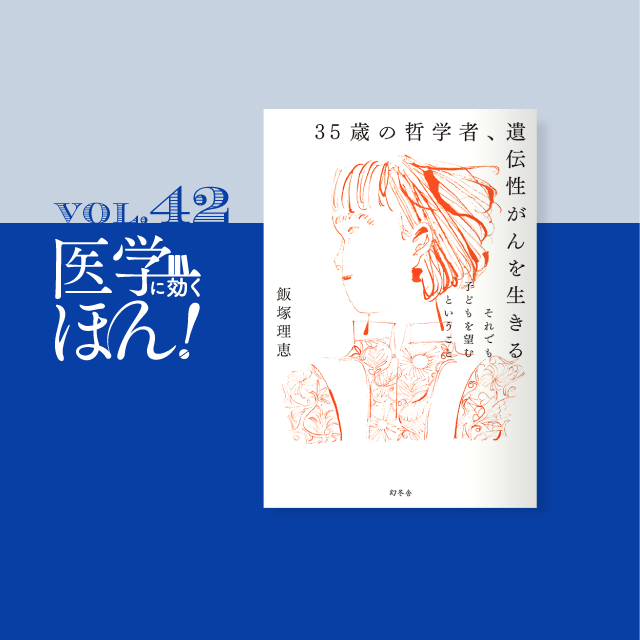睡眠は、古くて新しい医学研究テーマ。順天堂大学医学部、公衆衛生学講座の谷川武先生や和田裕雄先生も睡眠予防医学をご専門とされ、特に睡眠予防医学の研究成果を発表されたりしています。
本書『睡眠の起源』は、睡眠を研究されている東京大学の気鋭の研究者、金谷啓之先生が書かれた本で、金谷先生の昆虫大好き、研究大好きの幼少期からの生い立ちと研究内容を重ねつつ、金谷先生、そして世界の睡眠研究者が今、どんなことに注目して研究を進めているのか、一般読者にもわかりやすく解説されています。
睡眠とは、「意識状態の変容」である。そう、医学的には定義されています。もう少しわかりやすくいうと、起きている間に存在する意識が、眠っている間に減退します。でも、なぜ私たちは意識をもって、毎夜(人によっては毎朝?)、わざわざその意識を消失させているのでしょうか。金谷先生の研究では、ヒドラのような原始的な生物でさえ、睡眠をとっているような日内リズムがあることがわかっており、ネズミは眠らないとすぐに死んでしまうのだとか。なぜ、多くの生物は睡眠を必要としているのか。睡眠の間、脳内では体の中では何が起こっているのか。そもそも意識ってなんなのか。
睡眠を研究するということは、意識を研究することにつながり、私たちが存在する哲学的な意義まで考察するような壮大なテーマへと誘われるということです。
◆眠らないとヤバい、徹夜明けの頭は、泥酔状態
医学生は毎月、教科書数冊まるっと出題範囲、というような定期試験がやってきて、スポーツの部活に熱心な学生やバイトや課外活動に勤しむ学生は、数日前から徹夜でなんとかこの定期試験を突破しようとむちゃをすることも。でも、たいてい、うまくいきません(笑)
なぜなら、脳は、どうやら睡眠中に日中に見聞きした様々な情報を整理し、記憶を定着させているから。徹夜明けの脳の状態は、泥酔状態に近いらしく、そうなるともう試験を受けたとて、試験の問題が頭に入ってこず、ケアレスミスをしまくってしまうでしょう。
最近は、医師の働き方改革が進み、長時間労働が規制されはじめていますが、当直で一睡もできなかった外科医に執刀されるのは嫌ですね。
でも、なぜこんなにも私たちは睡眠に頼らざるをえないのでしょう?人生の1/3は眠りに費やすわけで、もっと睡眠時間を削られても大丈夫な身体だったら、今よりいろんなことができそうです。AIの長所は、休まず働けることで、身体を持つ私たちはそうはいかないところが、AIに勝てないひとつの大きな要因ですよね。
◆なぜ効くかわかっていない!吸入麻酔薬
睡眠を研究するポール・ショー先生は、「生物は眠っている方がデフォルトで、起きている方が特別である。」と語ったそうです。金谷先生が本書で紹介してくれています。
もしかすると、進化の道筋のどこかでもともと眠っていた生物が、“起きている状態”を作っていったのかもしれない。そんな仮説も睡眠研究では飛び出しているのだそうです。
ちなみに、本書でおしゃべり病理医が気になった話のひとつは、麻酔と睡眠の比較について。意識が消失している全身麻酔の状態は睡眠とはどう違うのかということが本書でも解説されているのですが、驚いたのは、なぜ、吸入麻酔薬が効くのかは、わかっていないのだそうです!吸入麻酔薬の標的となるタンパク質がいまだわかっておらず、麻酔の体内動態に不明な点が多いということ。わかっていないのに1840年代からずーっと使われているのが吸入麻酔薬なのです!!しかも、世界中では、毎年二億件以上もの手術が行われているという推計があるにもかかわらず、吸入麻酔薬が効かなかったという報告は、これまでに一度もないのだとか。吸入麻酔薬は、どう作用しているのかわからないけれど、100パーセント必ず効く薬ということ。これ、医学の超不思議問題の筆頭に上がるのではないかと思います!
金谷先生の本を読んで、睡眠についてますます興味を持ちました。研究者になりたいな、思う中高生のみなさんにも金谷先生の研究者としての姿がすごく参考になると思います。超おススメの一冊です。
◆バックナンバーはこちら
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』
- 2026.01.22お知らせ医療連携ゲーム「ENT!」の行く末は?今年度最後のMEdit授業@吉祥女子中学・高等学校
- 2026.01.19お知らせ1/21残席あり!W刊行記念トークライブ「法政大学元総長・田中優子×おしゃべり病理医・小倉加奈子」
- 2026.01.15ふしぎな医学単語帳ウワサの「直美」、解説します!