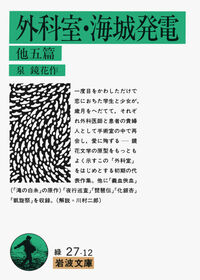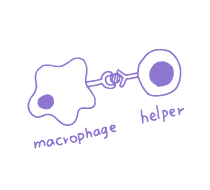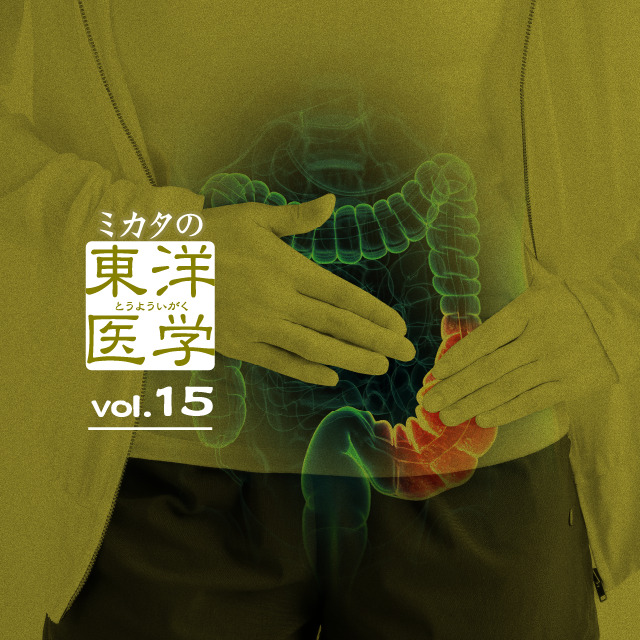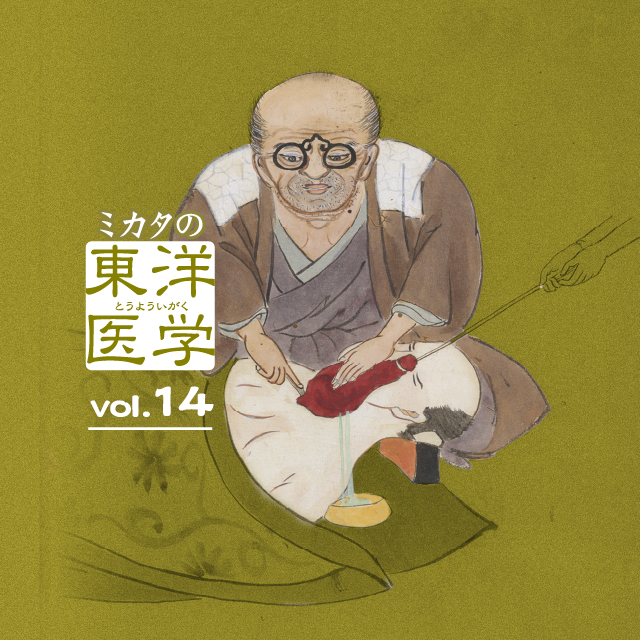手術の痛みを和らげる「麻酔」。金沢の明治時代の文豪・泉鏡花の『外科室』という短編小説では、とある婦人が頑として麻酔を拒否して手術に臨みます。その描写は読み手にも切迫感が伝わり、身の毛がよだつような緊張感に満ちています。この小説を読むと、当時にもし「鍼」麻酔が普及していれば、物語は違った展開になったのではないかと考えさせられます。
現在の手術では、西洋医学の全身麻酔や局所麻酔が当たり前のように使われています。でも実は、東洋には「鍼麻酔」という、全く異なるアプローチの技術があったのです。今回は、「ブロックの西洋麻酔」と「経穴の鍼麻酔」、それぞれの特徴を見ていきましょう。
◆西洋医学の麻酔 ─ ピンポイントで痛みをブロック
西洋医学では、痛みの信号が脳に届かないように、その経路を薬でブロックする方法を用います。昔のギリシャ・ローマ時代は、お酒や阿片(あへん)で痛みを抑えていたんですよ。現代のような麻酔が登場したのは19世紀になってから。1846年、アメリカの歯科医ウィリアム・モートンがエーテル麻酔を公開実演し、これが近代麻酔のスタートとなりました。
今、現在の西洋医学に基づく麻酔は、大きく「全身麻酔(意識を失くし、身体全体の痛みをシャットアウト)」と「局所麻酔(必要な部分だけの痛みを遮断)」に分けられます。手術の種類や患者さんの状態に合わせて、どちらかを選んで使います。
◆東洋医学の鍼麻酔 ─ 経穴(ツボ)からの痛み制御
一方、東洋では特定のツボ(経穴)に鍼を刺して痛みを和らげる方法を発展させました。この方法、なんと後漢時代(2世紀末〜3世紀初頭)の華佗(かだ)という三国志にも登場する医師がすでに手術に応用していたとされています。
現代の鍼麻酔が本格的に始まったのは1958年、中国でのことです。特に注目を集めたのが1971年。アメリカのニクソン大統領が中国を訪れた時に報道された鍼麻酔手術でした。ニューヨークタイムズの記者が中国で虫垂炎になり手術を受けた際に鍼麻酔が用いられ、高い鎮痛効果を実感したと報告しています。
◆科学で解き明かされる鍼麻酔の仕組み
最新の研究では、鍼による刺激が体内の天然の痛み止め物質「エンドルフィン」の分泌を促すことが分かってきました。特に注目されているのが、2001年に開発された「バトルフィールド鍼治療(Battlefield Acupuncture: BFA)」という技術です。これは、耳の5つの特定のポイントに小さな針を半永久的に留置する標準化された治療法で、短時間の訓練で習得でき、迅速に実施できるという特徴があります。
この技術は当初、軍事環境や救急部門での使用を想定して開発されましたが、その後の研究で、慢性痛や急性痛、手術後の痛み、さらにはがんに関連する痛みにも効果があることが報告されています。特に救急での急性痛の管理や、退役軍人の痛み軽減に関して、良好な結果が示されているのは興味深いところです。
ただし、なぜ耳のツボへの刺激がこのような効果をもたらすのか、その詳しい仕組みについてはまだ解明されていない部分が多く、研究結果にもばらつきが見られます。現在も、その効果の検証と作用メカニズムの解明に向けて、研究が続けられています。
耳の5つの特定のポイント(1. 帯状回(Cingulate Gyrus)、2. 視床(Thalamus)、3. オメガ 2(Omega 2)、4. ポイントゼロ(Point Zero)、5. 神門(Shen Men))
参考:Crowell MS, et al. The effectiveness of battlefield acupuncture in addition to standard physical therapy treatment after shoulder surgery: a protocol for a randomized clinical trial. Trials. 2020;21:1014.
◆新しい可能性を探る
いまでは、西洋医学の麻酔の欠点を補完するような東洋医学の麻酔の活かし方、使い方が研究されています。鍼麻酔は、手軽に行える点で医療設備が限られた地域でも使用でき、手術前や後の不安や痛みをコントロールできますし、麻酔薬の使用量を減らすこともできます。
西洋医学と東洋医学は、それぞれ異なるアプローチで痛みの問題に挑戦してきました。どちらが良いとか悪いとかではなく、状況に応じて使い分けることが大切なんです。また、東洋医学における痛み制御の仕組みを科学的に研究することで、新しい治療法の開発につながるかもしれません。痛みのコントロールは、今でも進化し続けている、とても重要な研究分野です。
◆「ミカタの東洋医学」バックナンバーはこちらから↓
投稿者プロフィール

- 生まれも育ちも石川県。地域医療に情熱を燃やす若き総合診療医。中国医学にも詳しく、趣味は神社巡りとマルチな好奇心が原動力。東西を結ぶ“エディットドクター”になるべく、編集工学者、松岡正剛氏に師事(髭はまだ早いぞと松岡さんに諭されている)。
最新の投稿
- 2025.07.14ミカタの東洋医学老いにはテンキをミカタに!
- 2025.06.30ミカタの東洋医学デジタル・デトックスは東洋医学だった? スマホ疲れを「陰陽」で読み解く
- 2025.05.15ミカタの東洋医学食事に含まれる謎の物質、約14万種!「医食同源」が証明される?
- 2025.04.03ミカタの東洋医学教えて、華岡センセイ!「便秘の治し方」