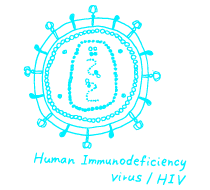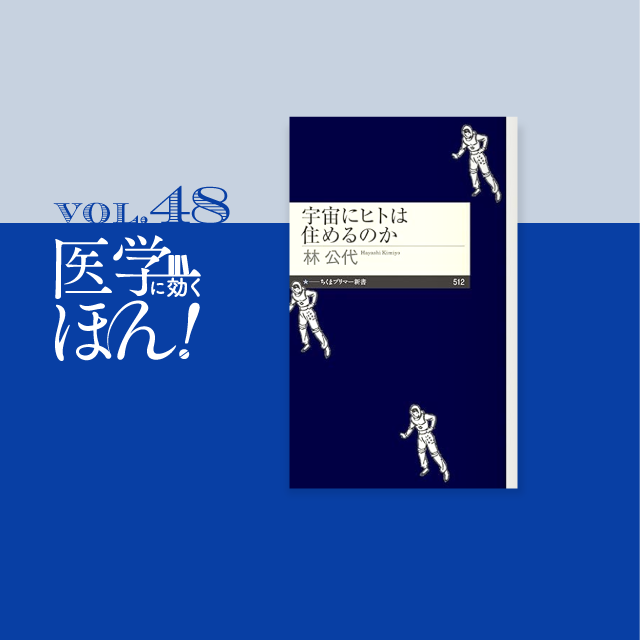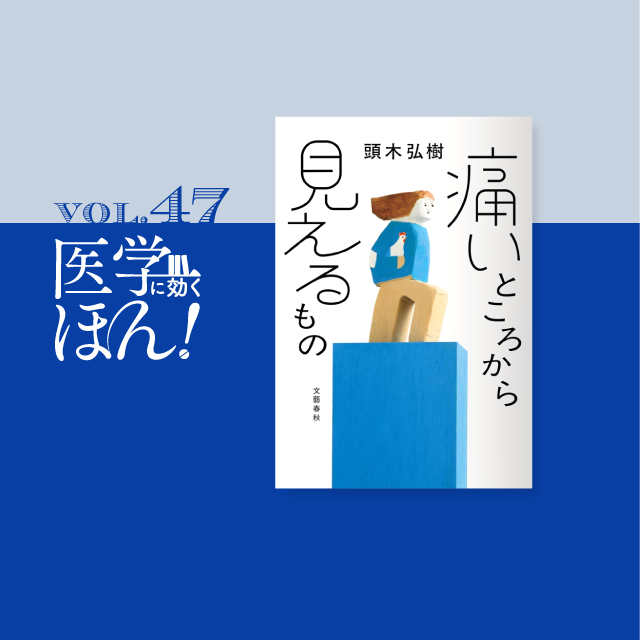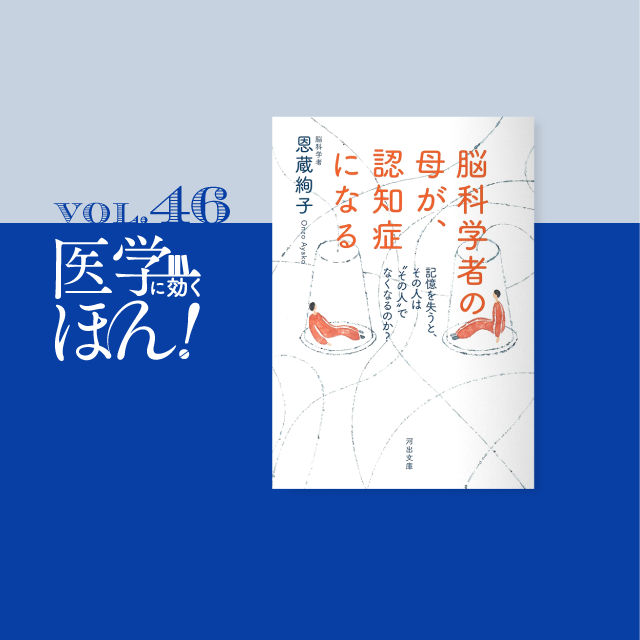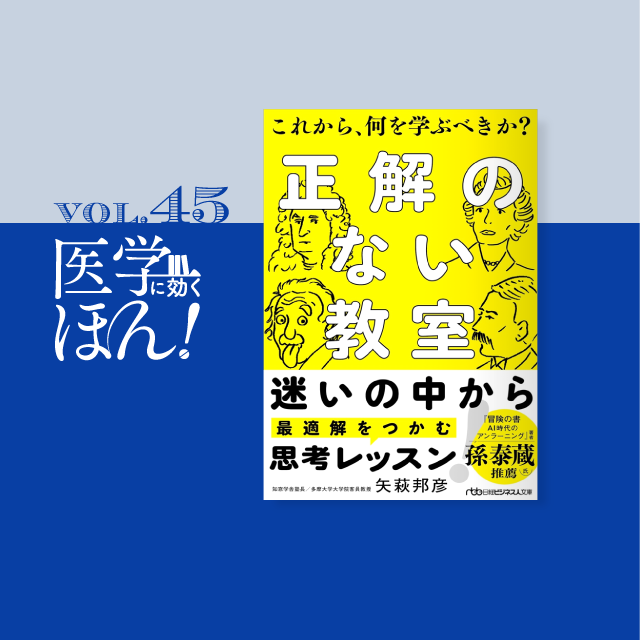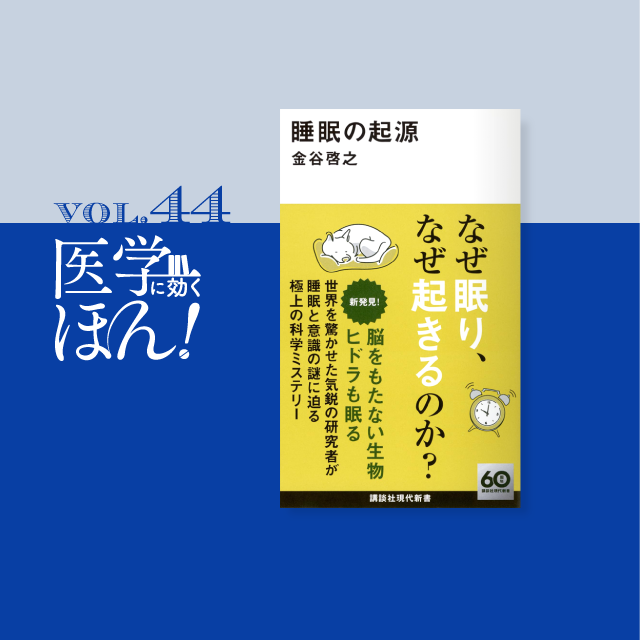医師を志望する医学部受験生たちは、「患者さんに寄り添う医師になりたい」と異口同音にいいます。もしかしたら、予備校で医師の志望理由を聞かれたり、どんな医師像が理想かといった質問にはそのように答えるのが無難だと教わっているのかもしれません。
では、“患者さんに寄り添う”というのは具体的にどういうことなのでしょう? 改めて考えると難しい。特に、もうこれ以上、治療の手立てがない終末期の患者さんにとって、いったいどんなことをすることが “寄り添い” なのでしょうか。簡単には答えられるものではありません。
ただ生きていられること、それがいかに難しく、有難いことか。こうして文字にすれば当たり前のことが、自分の血肉の感覚として理解できるということは、私にとって人生を生き直すくらいの重みがあった。
『透析を止めた日』の著者、堀川惠子さんは、透析患者であったご主人の過酷な最期を本書に克明に記録する中で、その看取りの日々を踏まえてこのように語っています。
◆緩和医療は、誰のため?
著者の堀川さんは、ノンフィクションライターであり、ドキュメンタリーを中心としたディレクターとしても活躍され、手がけた番組や著書で数々の賞を受賞されています。本書は、そんな堀川さんが初めて大切なご主人の看取りというご自分の体験を素材にして綴ったノンフィクションです。
最愛のご主人の壮絶な最期を公にすることには躊躇があったようですが、透析患者の、ことに終末期に生じる問題について、患者の家族の立場から思索を深め、国の医療政策に一石を投じようという想いで書かれた本です。
病理医の私のいる病理検査室は、透析室と同じフロアにあるのですが、本書は、こんなに近くにいるのに、これまで透析の実際についての自分の無知を痛感する読書となりました。
腎臓を悪くしたのはだらしない生活習慣のせい、などと透析患者さんが心無い批判にさらされることが少なくないという話は耳にしたことがありますし、週3回の透析を一度たりとも休むことは許されず(休むことは死を意味すること)、雪の日も嵐の日も透析クリニックに通い、4時間もかかる透析にじっと耐えることも知識として知ってはいました。
ただ、身体の状態が悪化すると、透析自体が非常に過酷なものとなること、また、透析の継続を断念し、尿毒症や皮膚の壊疽などの合併症になった場合の患者さんの耐えられないほどの苦痛、そしてそんな苦痛を和らげるための緩和医療が、がんや心不全の患者さんに限定され、腎不全の患者さんに適応されないことなど、知らないことだらけでした。医療制度がこんなにも矛盾に満ちていることは衝撃でした。
◆死について、ほとんど学ぶ機会のない医学生
近年、医学部で医学生が学ぶべき医学知識の量は膨大です。あるデータでは、医学知識が2倍になるのに要した時間は、2020年においてなんと73日だったのだとか!! 次から次へと新しい知見が登場し、医師になってからも生涯、学び続ける姿勢が求められる時代です。
一方で、医学部や現場で働く医師が、終末期の患者さんについて学ぶ機会はほとんどないといっても過言ではありません。病院では、とにかく「病気を治す」ことが最優先であり、患者さんが亡くなることは、医師にとって敗北を意味するだけのことが少なくなく、“どう死なせたらいいか”ということに真剣に向き合う機会はほとんどありません。治療の手段がない患者さんに対してどんな医療が望ましいのかを学んだり考えたりする時間が少ないということに、本書を読んで改めて気づかされました。
本書の帯にはこうあります。
私たちは必死に生きた。しかし、どう死ねばよいのか、それが分からなかった──
今の医学教育において、もっとも足りていないのは、この疑問に対して答えられる医療従事者の育成ではないかと感じます。
◆「医学に効くほん!」バックナンバーはこちらから↓
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.02.19ふしぎな医学単語帳やる気がないと思われちゃう?「起立性調節障害」
- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』
- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』