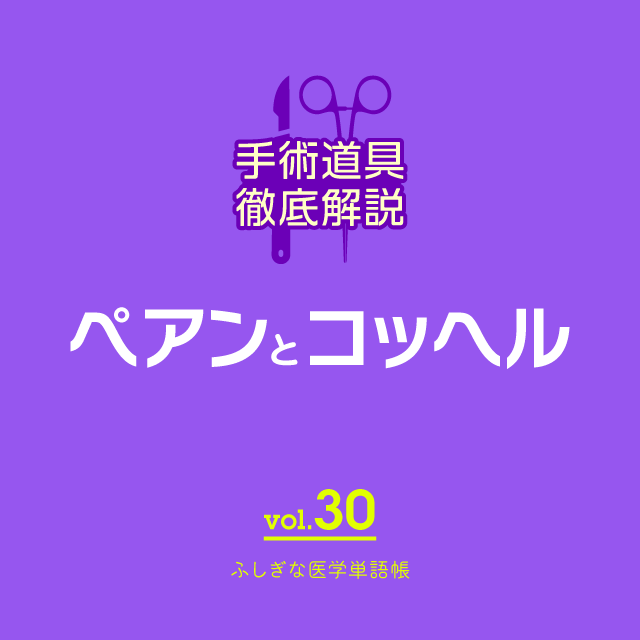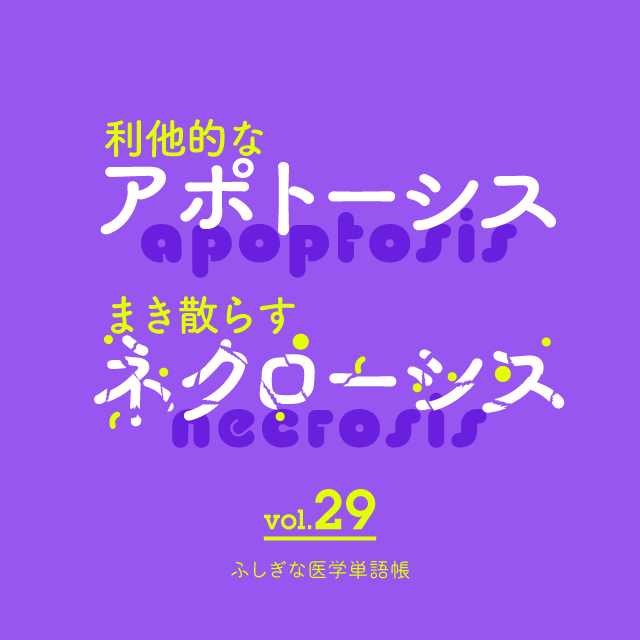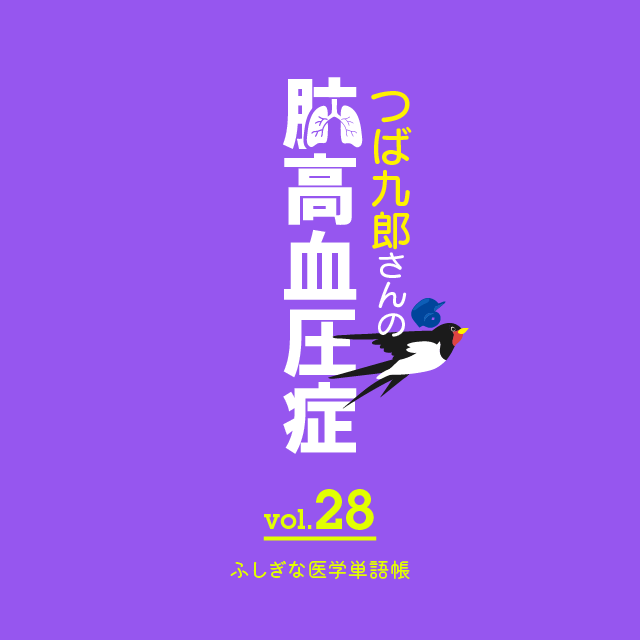2023年の日本人の死亡原因第3位に浮上した「老衰」。老いて衰える。老衰で亡くなったと聞くと病気をせずに大往生して安らかにお亡くなりになったのかというような比較的ポジティブな雰囲気もあるかと思うので、老衰って病気じゃないんじゃ…というイメージもあるのではないでしょうか。
実は、「老衰」という病態に対して明確に答えられる医師はほとんどいないのではないかと思います。医学部の授業を振り返っても、老衰をきちんと習った記憶はありません。おしゃべり病理医としんしんは、病理解剖を行い患者さんの死亡原因を特定する仕事もしていますが、正直なところ、解剖の結果、老衰と記載したことは一度もありません。そこで、おしゃべり病理も老衰について、ちょっと調べ学習をしてみましたので、今回はその結果をご報告したいと思います。
◆老衰は医学用語じゃない…?のか?
さて、「老衰」という言葉をネット検索したり、教科書などを調べてみたのですが、改めて驚くのが老衰という言葉は、ほとんど説明されていません。老衰は医学用語ではないのかもしれないと思えてきました。
こんな時に頼りになるのが辞書。『日本大百科全書』には、このように説明されています。
生体が老化し、全器官・組織に老人性退行性変化が進んで衰弱した状態
そうか。「老化」はかなり今、ホットな医学用語です。全身の老化が進んだ結果と考えられる死亡を老衰というのか。ちょっとだけ理解が進みました。
◆じゃ、老化って何?
老化は、癌の発症リスク、フレイル、認知症といった高齢化社会がもたらす諸問題がより深刻になってきていることと、老化のメカニズムが遺伝子レベルで解明されるにしたがって、医学研究の中でもかなり主要なテーマとなっています。
老化の研究は、1882年にWeismann博士が、「加齢に伴う消耗した組織が臓器不全の基礎となる」という“消耗仮説”を提唱したことにはじまります。その後、Hayflick博士が、細胞分裂回数には限界があることを証明し、細胞老化の概念が提唱されます。
さらに、その16年後の1987年にGreider、Blackburnの両氏が「テロメラーゼ」を発見し、両博士は2009年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。テロメラーゼとは、生物を勉強したことがある方はご存知かと思いますが、テロメアを分解する酵素のこと。テロメアとは、染色体の末端にあるDNAとタンパク質からなる構造で、染色体がまっすぐの形状に保たれるように維持する働きがあるのですが、細胞分裂のたびに、このテロメアが少しずつテロメラーゼによって分解されていき、ある回数に達すると細胞はそれ以上分裂することができずに細胞死をむかえます。これが老化のメカニズムの大きな要素のひとつであるといわれています。また、がん細胞はこのテロメラーゼに抵抗する力を有しており、いくらでも分裂できるようになってしまっていることがわかっています。
◆なぜ、老衰が増えているの?
おっとっと。老化の話ばかりになってしまいました。老衰とは、全身の細胞の老化によって、身体機能が衰えて死んでしまうことということがわかりましたが、医師が死亡診断書に「老衰」と書くのはかなり限定的な状況ではないかと思います。
実際、医療技術が進歩してからは、高齢の方の死因について安易に「老衰」と書くことは避けられてきましたし、今でも病理解剖の結果、「老衰」とは書きにくいなと思います。
上記のような状況下で、死因の第3位に「老衰」がランクインしたのは本当に驚きました。
理由はいくつか考えられます。まずひとつは、日本が超高齢化社会に突入していて、自然死≒老衰とするしか考えにくい事例が多くなっていること。また、高齢となったら、無理な治療はせずに自然な死を受け入れようとする人が増えてきたこと。それにあいまって、医師の方も少しずつ、老衰という言葉を死因として受け入れられるようになってきている、ということがあげられます。
日本の死因の第一位が「老衰」になることもそんなに遠い将来ではないかもしれません。
◆参考URL
厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)の概況」gaikyouR5.pdf
◆バックナンバー
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』
- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』
- 2026.01.22お知らせ医療連携ゲーム「ENT!」の行く末は?今年度最後のMEdit授業@吉祥女子中学・高等学校