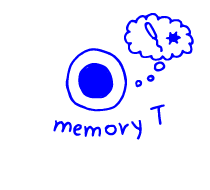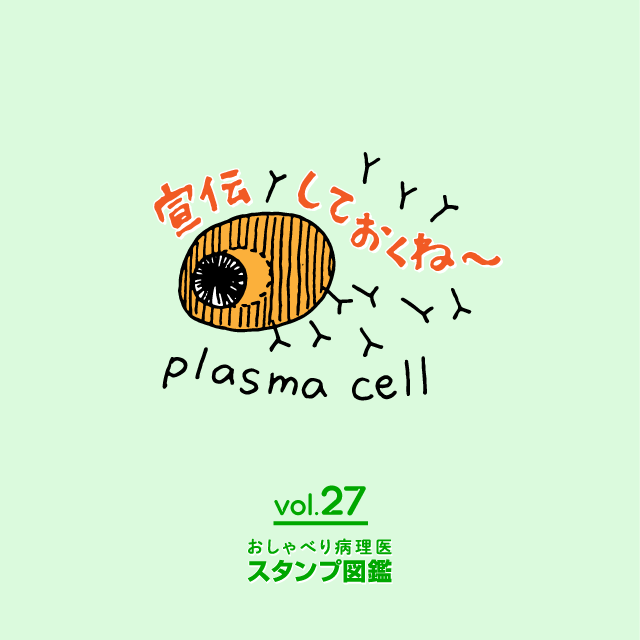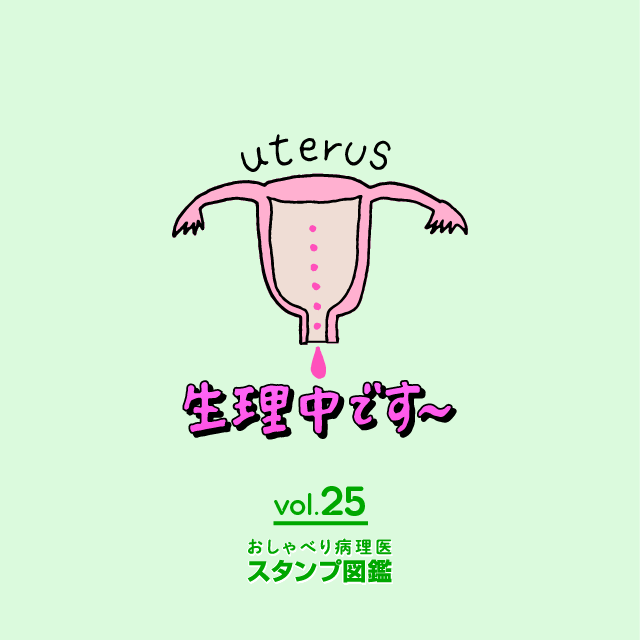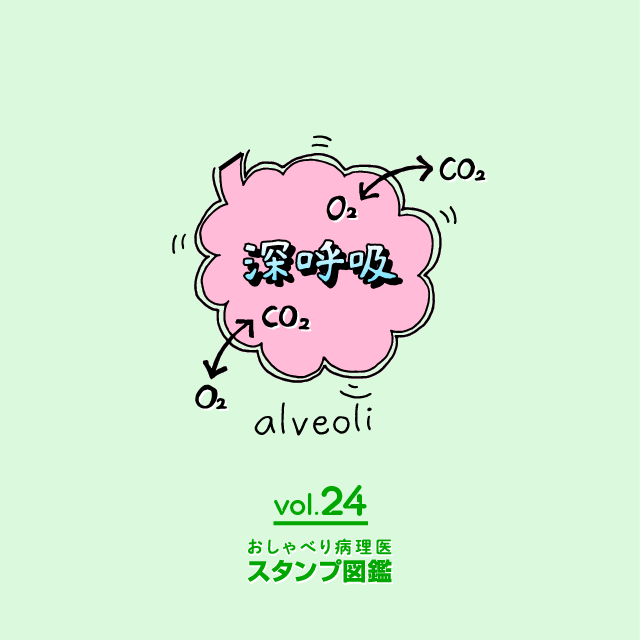ドラえもんに登場するのび太くんは、しょっちゅうおねしょをして、ベランダに濡れた布団を干されてみんなにからかわれていますが、みなさんもおねしょの思い出はあるでしょうか?
今日の「おしゃべり病理医スタンプ図鑑」は、「トイレ、行ってきま~す!」のスタンプとともに、主におねしょのお話をしたいと思います。
おねしょの正式名称、医学用語は「夜尿症(やにょうしょう)」です。一般的に、満5歳を過ぎてもおねしょをしている場合に、一応「夜尿症」の診断がつけられるのですが、小学校に入る前までに少しずつ、おねしょの回数が減っていき自然とおねしょをしなくなる方が多いといわれています。日本小児泌尿器科学会によると、7歳児の夜尿症のお子さんは10%程度とされ、その後、年間約15%ずつ自然治癒していき、成人に至るまでにほぼ全例が治癒するのだそう。のび太くん(原作では小4)はちょっとレアで、移動教室などでお泊りの機会もあるため、小児科の先生としては治療をしてあげたいと思うケースです。
◆なぜ、おねしょしてしまうのか?
大人になっても夜に尿意を催してトイレに行くことはあります。つまり、「トレイに行きたいな」と目覚めて、トイレに行って用を足すことができれば、おねしょにはなりません。おねしょする状態とは、尿意に気づかないでお布団を尿で汚してしまうことを意味します。
おねしょをしてしまう要因は大きくふたつあります。
ひとつは、尿量を減らす働きのある「抗利尿ホルモン」が夜にしっかり分泌されないこと、もうひとつは、膀胱で貯められる尿が少ないことです。ふたつの要因が重なっているお子さんもおられるのだそう。
通常、大人の場合は、「抗利尿ホルモン」が昼間は少なく、夜間に多く分泌されるという日内リズムがあり、夜、睡眠している間、尿量が少なくなるように調整されています。朝起きて、最初の尿は、とても濃い色をしていますが、尿が濃縮された証拠です。また、膀胱は尿意を催して、排尿するときにきゅっと収縮し、それ以外は、尿をしっかり溜められるようにゆるんでいます。小さいうちはその機能が未熟なため、夜に尿を貯められる量が少ないのです。
◆どんな治療をするの?
さて、どんな治療をするのでしょうか。まずは、生活習慣の見直しです。眠る直前まで、飲んだり食べたりしていれば、その水分は約2時間後に尿になります。ですから、夜はなるべく早めに飲んだり食べたりするのをやめて、規則正しい生活を送ることが大切。また、しっかりトイレにいってから、眠るという習慣も大事です。うっかり、トイレに行かず眠ってしまうと、真夜中に大惨事ということになりかねません。
それだけで、おねしょが治る方がおられるのだとか。でもそれでもすっきり改善しない場合は、夜間の尿量を少なくするようなお薬が処方されることもあります。
もうひとつユニークな治療が、「アラーム療法」。夜、睡眠中におもらしの始まった時、パンツに装着したアラームのスイッチが入り、お子さんを音や振動で起こさせるもの。おしっこがちびりそうな予感?を察知する力を養うというアプローチで、自力で目覚め、トイレに行けるよう促す方法です。これ、なんだか自信がつきそうな気がします。実際、3か月で60%程度のお子さんに有効なのだとか。海外では、薬物療法より、まずはアラーム療法がおこなわれることも多いそうですよ。
そういえば、トレパンマンは、おむつでおもらししても漏れることはないけれど、濡れたことがわかるような特別な材質で作られていますよね。これは起きている時のトイレトレーニングですが、アラーム療法は眠っている時のトイレトレーニングなのか!なるほど。
お子さんのおねしょで悩むお父さん、お母さんは、ぜひ小児科の先生に頼りましょう。
◆参考URL
夜尿症 | 小児泌尿器科の主な疾患 | 日本小児泌尿器科学会 Japanese Society of Pediatric Urology
◆おしゃべり細胞スタンプは「こちら」 ←クリック♪
◆「おしゃべり病理医スタンプ図鑑」バックナンバーはこちらから↓
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.02.19ふしぎな医学単語帳やる気がないと思われちゃう?「起立性調節障害」
- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』
- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』