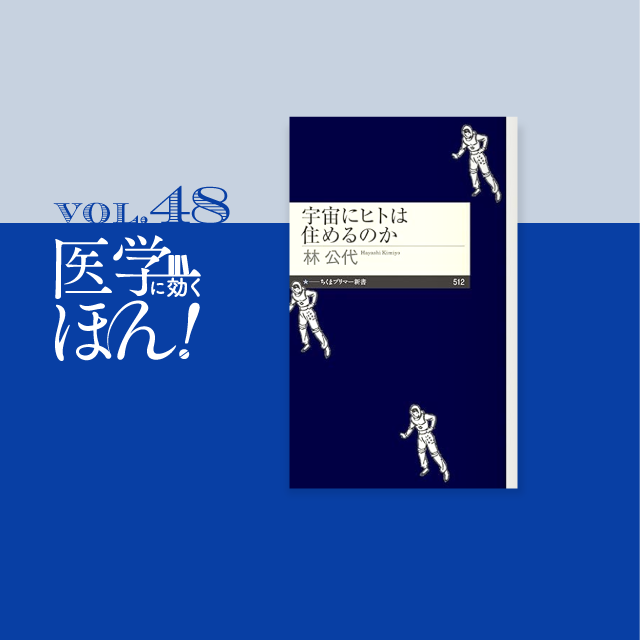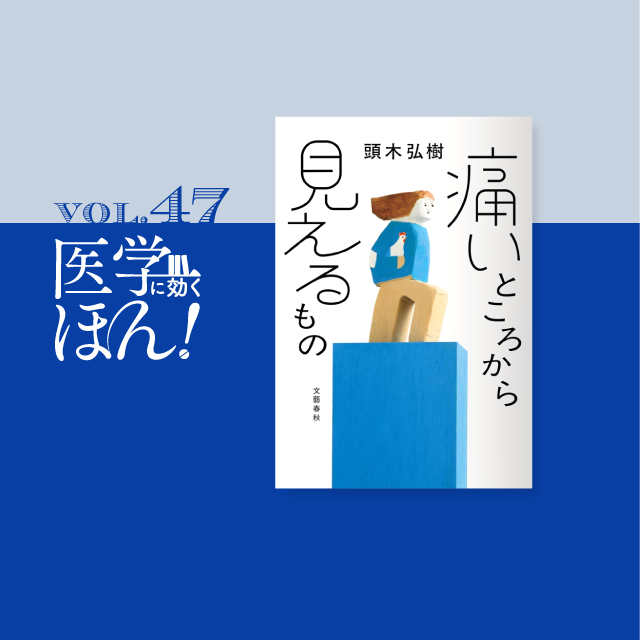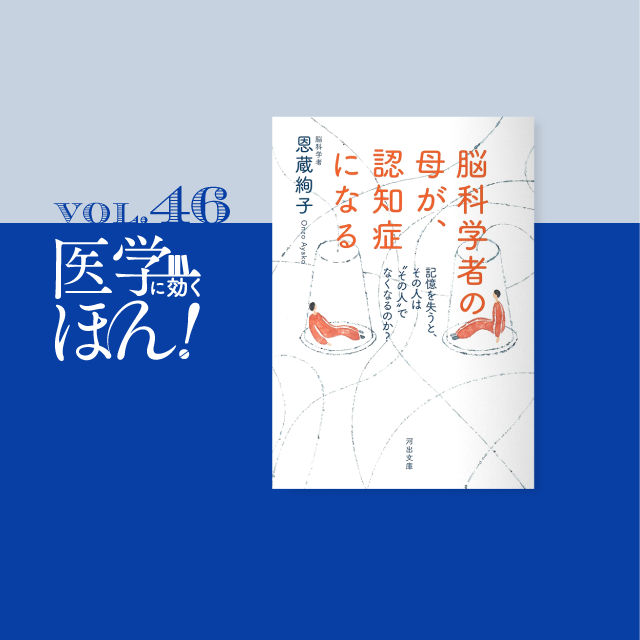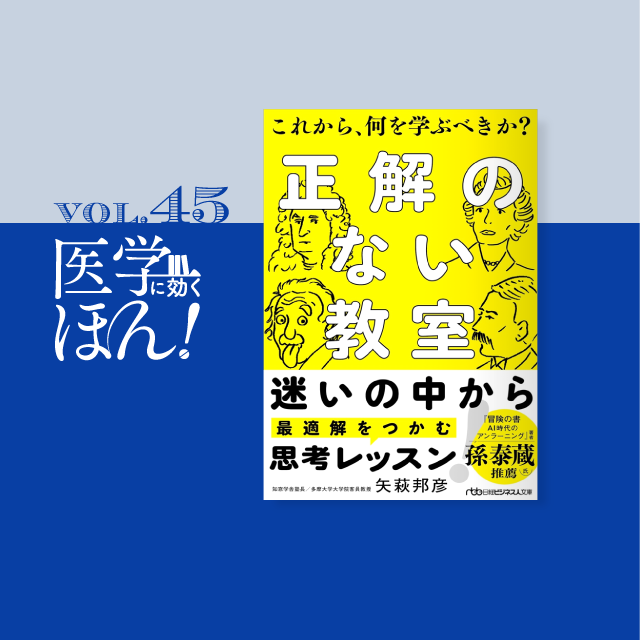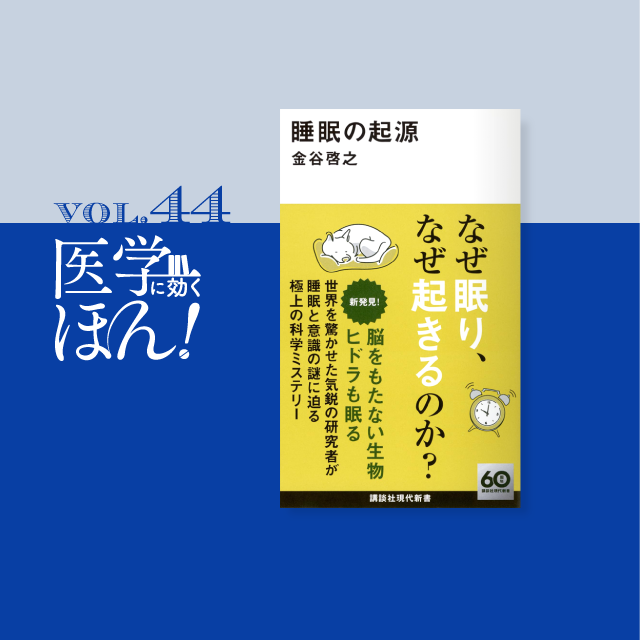米国の女優、アンジェリーナ・ジョリーが、乳癌と卵巣癌の発生が高くなるとされる遺伝子「BRCA1」に変異があるとして、乳癌予防のために両乳腺を切除する手術を受けたことを明かしたのは、2013年。このニュースをきっかけに、家族性の遺伝するがんについての議論がホットになりました。特にここ数年は、医療現場でどんながんの診断においても遺伝子検査が当たり前になってきて、じょじょにですが、遺伝性のがんであることを告知された患者さんをサポートする遺伝カウンセリングも整備されつつあります。
本書『35歳の哲学者、遺伝性のがんを生きる』は、タイトル通り、哲学者である著者の飯塚理恵さんが32歳で遺伝性乳がんと診断され、治療や様々な検査を受けた約3年間の日々を綴り、遺伝子検査にまつわる様々な課題についてまさに哲学者という視点から考察をしたエッセイです。
たしかに私の勤めている大学病院においても乳がん患者さんは非常に多く、私たち病理医は、ほぼ毎日、何人もの乳がん患者さんの生検(手術前の乳がんであるか否かを確定する病理検査)や手術検体(がんの大きさやリンパ節の転移の有無など、主にがんの広がりを診断する病理検査)の病理診断を担当していますが、30代の若い患者さんも少なくないなと思っています。
そんな若年発症の乳がんの患者さんの中には少数ですが、アンジェリーナ・ジョリーや飯塚さんと同様に、BRCA遺伝子に変異を持つ「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(Hereditary Breast and Ovarian Cancer: HBOC)」の方がおられます。HBOCは、乳がんや卵巣がんにかかるリスクが顕著に高くなる遺伝病で、実は、他の臓器のがんにかかるリスクも同時に高いため、一生、がんにかかりやすい体質を抱えて生きていくことを迫られる過酷な疾患です。
さらに、AYA世代といって妊娠・出産が可能な時期とがんの治療が重なってしまうことも少なくないために、若い患者さんがお子さんを希望すれば、抗がん剤治療の前に採卵をして凍結保存することによって、治療が終わった後の妊娠・出産に備えることが一般的に行われています。
◆着床前遺伝学的検査と優生思想
本書では、そのさらに先、採卵された卵子に対する「着床前遺伝学的検査」について詳細なレポートがなされています。たしかにHBOCの患者さんがお子さんを生んだ場合、50%の確率でBRCA遺伝子がお子さんにも遺伝してしまうわけです。患者さんは、母として自分と同じ不安を抱える遺伝子を子どもに遺伝させたくないと思うことは自然なことでしょう。ただ、日本では「着床前遺伝学的検査」については大きな制約があり、その課題についても当事者となった飯塚さんが哲学者の視点で、真摯に考察されています。
素敵なご主人と出会って結婚し、お子さんを持つ夢を膨らませながら哲学者としてキャリアをスタートさせようとした矢先のがんの告知。飯塚さんのがんは、悪性度が高いがんで、リンパ節にも転移があり進行がんであったため、抗がん剤を含めた過酷な治療が必要でした。その中で、お子さんを持つ望みを捨てずに、「着床前遺伝学的検査」を受けるまでの経緯が本書では語られていますが、特に多くの方に読んでいただきたいのは、第4章「遺伝性がん患者に『生殖をめぐる自己決定権』はないの?」です。
この問題で登場するのが、「優生思想」。歴史上、最も悪名高いのはナチスドイツの政策です。アーリア人が最も優れているという優生思想のもと、主にユダヤ人を迫害したことは歴史の授業の中でみなさんも学んだことのある史実ですね。ただ、こういった極端な優生思想だけではなく、私たちは優生思想的な取り組みの恩恵を実は無意識に受けています。野菜や果物の品種改良はまさに人間が美味しく食べられるためという点で、「望ましい特性を持つ個体を選別して交配させ、次世代に良い特性を持つ個体数を増やす」優生思想的な取り組みであるといえます。
飯塚さんはさらに、恋愛自体も見方によっては「弱い優生思想」と言えるのではないかと指摘します。「良い学校に進学してほしいから塾に入れる」といった子育てにおける親の教育方針においても、私たち人間は多かれ少なかれ、弱い優生思想を含むような好みを抱き、そうした考えに基づく実践をすでに行っているといいます。
そういった考察を踏まえて「着床前遺伝学的検査」についての是非について飯塚さんは考察を深めます。
「カップルが、産む可能性のある子どもの中から、最善の人生を送ることが予想される子ども、または、少なくとも他の子どもたちと同程度に善い人生を送ることが予想される子を選ぶ」ということは、倫理的にどうなのか。飯塚さんが本書で行き着いた“ひとまずの結論”(飯塚さん自身、また時が経った時に自分の意見が変わる可能性があることも正直に述べられています)に関しては、本書で確認いただくとして、みなさんはどう考えますか。
また、飯塚さんのように悪性度の高い進行がんにかかり、40歳まで生きられるかどうかわからないという状況の患者さんが子どもを望む、ということに対してどのように考えますか。飯塚さんも「がん患者が子を望む」というわたしの選択を哲学的に考える、という命題を自分自身に投げかけて考察されています。
答えは簡単には出せない問いですが、日本においてはこういった問いが議論になること自体があまりにも乏しいように思います。多くの方に読んでいただきたい一冊です。
◆バックナンバーはこちら
投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。
最新の投稿
- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』
- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】
- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』
- 2026.01.22お知らせ医療連携ゲーム「ENT!」の行く末は?今年度最後のMEdit授業@吉祥女子中学・高等学校