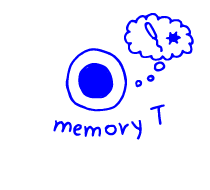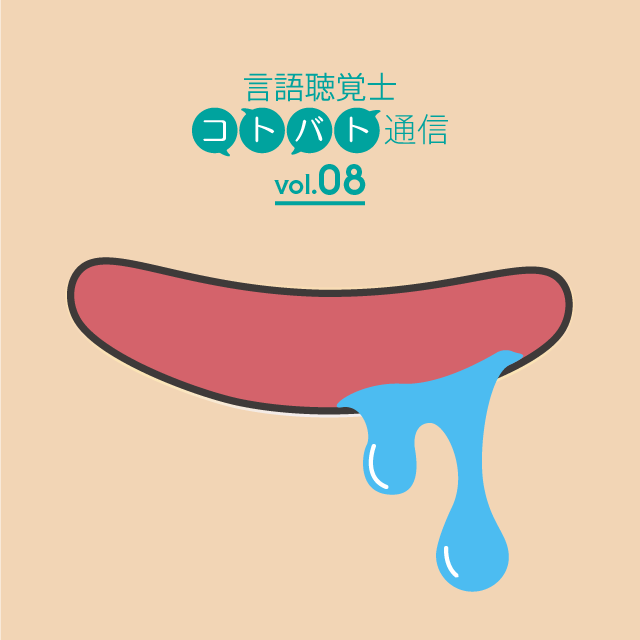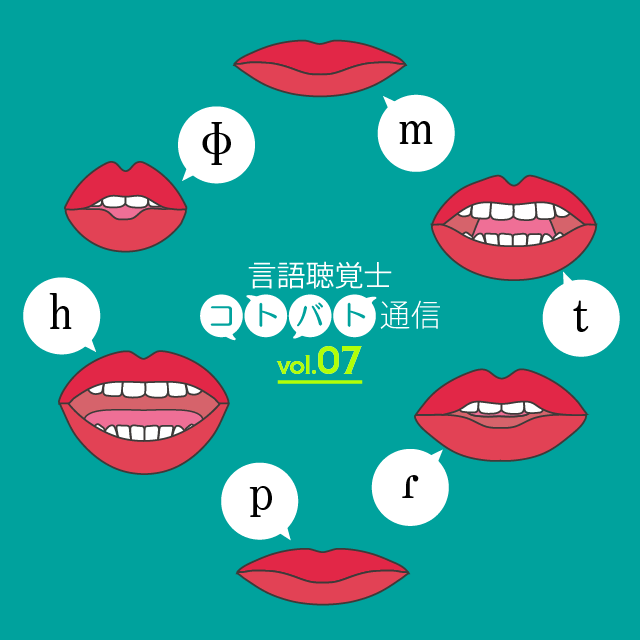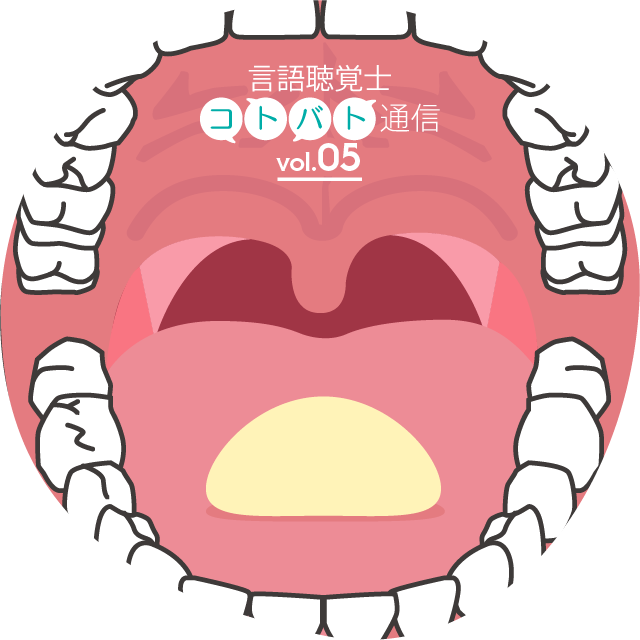コトバト通信 COLUMN
こんにちは、言語聴覚士の竹岩直子です。
以前お話しした通り、言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist、ST)は、「話す」「聞く」「食べる」を支えるリハビリの専門職です。
では実際に、どんな場所で、誰と、どのような仕事をしているのでしょうか。今回は、私自身の経験も交えながら、その一端をお伝えしたいと思います。
◆言語聴覚士の職場
全国の言語聴覚士のうち、半数以上は総合病院やクリニックといった医療施設で働いています。
そのほか、介護・福祉施設、教育機関(小学校や特別支援学校)、行政(市役所・保健センター)、さらには補聴器メーカーや教材関連の一般企業など、活躍の場は多岐にわたります。
同じ資格でも、働く場所によって仕事内容も、共に働く仲間も大きく変わるのがこの職種の特徴です。
◆私の働く仕事場
私自身も、いくつかの異なる場所で働いてきました。
たとえば、総合病院のリハビリテーション科では、嚥下障害や失語症、高次脳機能障害の患者さんに、理学療法士や作業療法士と連携しながらリハビリをおこないます。
医師(呼吸器科、脳神経内科、小児科など)に評価や訓練の報告をおこなったり、患者さんに合う食事の形態を評価して、看護師さんや管理栄養士さんと共有したりもします。
また、ある大学病院では、歯科医師と協働し、構音障害(発音の問題)に対する評価や訓練をおこないます。患者さんは、口腔癌や舌癌の手術後の方から、赤ちゃんことばがなかなか上手にならない小さなお子さんまでさまざまです。
そのほか、訪問リハビリでは退院後の失語症の方とかかわり、ご家族も含めた生活支援をおこないます。
さらに、専門学校の講師として、言語聴覚士を目指される学生さんに臨床場面のリアルを伝えたり、市民講座の講師として誤嚥予防についてお話したりもします。
最近ではオンラインリハビリに挑戦中で、歯科医師と連携しながら小児の構音(発音)指導にも取り組んでいます。
こんなふうに、一つの資格でありながら、医療・教育・地域のさまざまなフィールドで活躍できることも言語聴覚士の大きな魅力だと感じます。
◆連携の必要性
多くの職場に共通することは、一人の患者さんを中心に、異なる専門職が意見を交わしながら協力するチームの連携があることです。
医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士など、私たちは多職種と密に関わりながら、患者さんの「ことば」や「食べる力」を支えています。
専門分野ごとに見ている視点が違うからこそ、新しい気づきが生まれ、より良い支援につながります。言語聴覚士の仕事は、チームの中でこそ生きてくるのです。
◆まだまだ少ない言語聴覚士
2025年現在、日本全国に約4万3千人の言語聴覚士がいます。
同じリハビリ職種である理学療法士が21万人、作業療法士が11万人を超えることを考えると、その数はまだ多くありません。国家資格化が1997年と比較的新しいこともあり、今もなお人材が求められている職種です。
そのため、職場を超えて相談し、経験を共有できる言語聴覚士同士のつながりはとても貴重です。互いに学びあうことは、日々の仕事に新しい風を吹き込みます。その風が患者さんや家族のもとへ届くことを願いながら、日々の仕事に向き合っています。
◆おわりに
言語聴覚士の仕事は、目立つものではありません。
けれど、人の「ことば」や「食べる喜び」に関わることのできる、かけがえのない仕事です。
これから医療の道を志す皆さんに、ぜひ、「話す」「聞く」「食べる」を支えるこの世界に、少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。
それでは、今回はこのへんで。また次回お会いしましょう!
◆参考URL
◆バックナンバー「言語聴覚士コトバト通信」はこちら
投稿者プロフィール

- 絵本作家に憧れていたという少女は、若干、変化球的に進路を選択して「言語聴覚士」に。コトバのセンスがバツグンのマイペース大阪人で趣味は刺繍と空想。おしゃべり病理医おぐらとは「イシス編集学校」の仲間。
最新の投稿
- 2025.11.17言語聴覚士 コトバト通信いったい何者? 言語聴覚士
- 2024.12.05言語聴覚士 コトバト通信うずまきの秘密
- 2024.07.25言語聴覚士 コトバト通信唾液のチカラ
- 2024.02.19言語聴覚士 コトバト通信そのことば、どんな音?