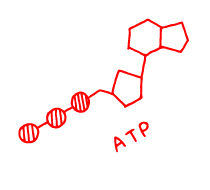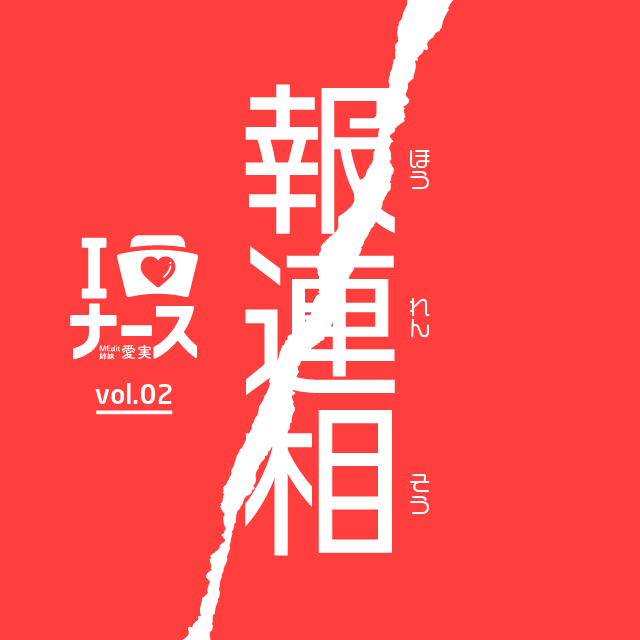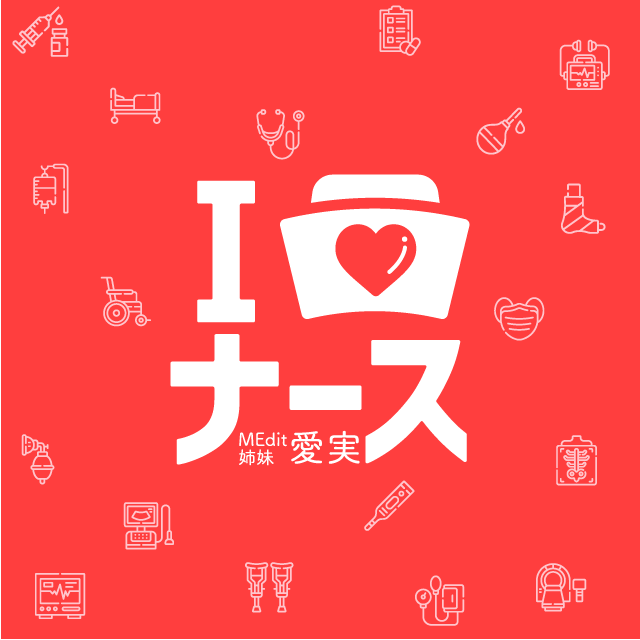「看護師って、医者の指示を聞いて動く人でしょ?」
そんなふうに思っている人、意外と多いのではないでしょうか。でも、実際の現場で看護師がやっていることは、もっと幅広く、もっと主体的です。
◆部署ごとに違う「顔」をもつ看護師
看護師と一口に言っても、働く場所によってその姿は大きく異なります。患者さんと接する時間の長さ、求められる判断力や技術、チーム内での役割――それぞれの現場で「看護の顔」が変化します。
病棟では、食事や清潔のケアに加え、点滴や服薬を見守りながら、患者さんの生活を支える看護師がいます。一方、ICUはモニター音の絶えない緊張の空間。秒ごとに変わる容体を見つめ、医師と呼吸を合わせて救命に挑む。手術室では、器械を次々と渡す手の動きと、外回りで全体を見守るまなざしが交差します。声を出さずともチームの呼吸がそろうのは、長い訓練のたまものです。そして救急外来。予測できない患者の到着に備え、瞬時の判断で処置へとつなげる。その裏で、不安や怒りを抱えた家族の声に耳を傾けるのもまた看護師の仕事なのです。
◆患者の思いを伝える代弁者(アドボケーター)
では、看護師は医師とどう関わっているのでしょうか?
医師が治療方針を立てるとき、看護師は「その患者さんが本当にできるか」を現場の目で伝えます。例えば、薬の副作用で食欲が落ちていて必要な栄養がとれない、家では手を借りられる人がいない、など。看護師の日々の観察した情報から、医師が治療方針を変更することも多々あります。診察室や手術室で医師の「右腕」となるだけでなく、患者さんの「声」を代弁する役割も果たしているのです。
患者さんは、必ずしも自分の思いを言葉で上手に伝えられるとは限りません。患者さんの“声にならない声”を拾い上げて医師や医療チームに伝えるのは、看護師の大切な役割の一つです。これを「アドボカシー(advocacy)」=代弁すること、と呼びます。
たとえば、入院中の患者さんにとっては、「退院後、また仕事に復帰できるだろうか」「子どもの世話はどうしよう」といった生活上の不安が、病気と同じくらい大きな問題になることがあります。
私も15年以上前、21歳の時(まだ大学4年生でした!)に病気を発症したばかりの時は、動揺しました。気管切開の手術後は発声をすることもできず、筆談の期間は1ヵ月。また、気管に入れているカニューレが異物であることから、身体の外に出そうと痰も30分~1時間毎に吸引が必要な状態でした。このまましゃべれなかったら、吸引が必要な状態が続いたら、私はどうなるんだろう、何ができるんだろう…と、涙がこぼれる毎日でした。
しゃべれるようになりたい、筆談で伝えた私の想いを膠原病内科の医師に伝え、ともに真剣に考えてくれたのが看護師でした。膠原病内科、呼吸器内科、耳鼻科と多科に跨って調整が必要な状態だったのは言うまでもありません。私のカニューレは、より生活に支障の出ない形のものへ、4種類ものカニューレを経て今の形に落ち着きました。
また、看護師たちは、私の退院を見据えて気管内吸引を自分でも行えるよう、一から必要な技術を教育。理解度を確認しながら見守り、独り立ちできるようサポートに徹してくれていました。病院と在宅では物品の消耗の仕方が全く異なるので、在宅に合わせて教育してくれました。吸引用のカテーテルを例に挙げると、病院ではディスポーザブルで、単回使用ですが、在宅では1日1本で消毒しながら何回も使います。自分自身で手技を獲得して、自宅に戻れたことは、まぎれもなく私自身の自信に繋がりました。
看護師は患者さんが地域に戻ることを具体的にイメージした“生活の視点”を忘れずに、患者さんを全人的に理解し、支えていきます。
◆ナースステーションの舞台裏
ナースステーションは、病棟の“頭脳”ともいえる場所。
パソコンの画面に向かいながら、医師の指示を確認し、薬剤や処置の準備を行います。電話が鳴れば患者家族の問い合わせに応じ、廊下から「すみませーん!」と呼ばれればすぐに席を立つ。患者さんからは見えにくいナースステーション内では、看護師たちが交代で患者さんの状態を報告し合い、看護計画を立てています。
「この患者さん、昨日はよく眠れていなかったから、今日は環境を工夫しよう」
「薬の影響で転倒リスクが高まっているから、見守りを強化しよう」
ここでは「情報を整理し、全体を見渡す調整」を行っています。お互いにコミュニケーションを取るために、行き交う言葉。学生の時に初めてナースステーションに足を踏み入れた時は、正直に言うと、あまりの騒がしさと、交わされる情報量の多さ、空気感に圧倒されてしまいました。医療チームでお互いの意見がぶつかり合うこともしばしば。それだけ医師と看護師、医療チームは「上下関係」ではなく、お互いに補い合う専門職なのです。
こうして緻密に計画を練り、それぞれの立場から交わされる情報を、チームで共有し動くからこそ、医療は安全に回っているのです。
ここで紹介できたのは看護の仕事のほんの一部。私達は専門職として、医師とも対等に意見し、時にはぶつかり合いながらも、患者さんにとって何がベストか、協力しながらケアをしています。世間では「白衣の天使」なんていわれますが、臨床現場の看護師は「強くて、逞しく、かっこいい」のです。
◆参考文献
1.日本看護協会『看護の定義』https://www.nurse.or.jp/
3.日本看護協会『看護職の倫理綱領』
https://www.nurse.or.jp/nursing/rinri/text/basic/professional/platform/index.html
4.『ナースが学ぶ「患者の権利」講座:アドボケイトになるための25の心得』
著者:隅本邦彦 出版社:日本看護協会出版会(2006年刊)
◆バックナンバー
投稿者プロフィール

- 勇気とガッツと愛嬌で難病を克服し、看護師の道へ。想像力と創造力がモットーで、プログラミングや動画編集もできちゃうアーティスト。愛犬と爆睡してエナジーチャージ。仲良しの妹は臨床検査技師。
最新の投稿
- 2025.10.06I♡ナース医者のお手伝いじゃありません、看護師のリアルな仕事
- 2025.09.08I♡ナース患者さんにとっての恵みの雨「シャワー浴」
- 2024.11.18I♡ナースお口から輝け!「看護師の口腔ケア」
- 2024.04.22I♡ナース医療現場の「ほうれんそう」は難しい。ではどうする?